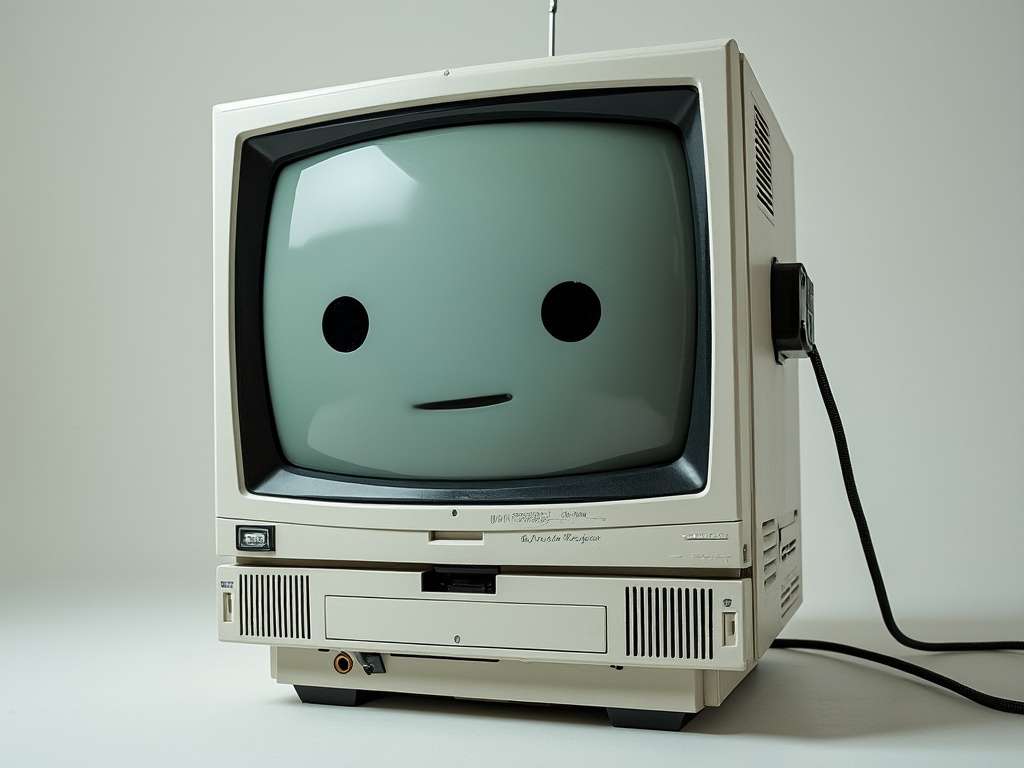不可思議な世界を生きていることを認識して生きている人はあんまいない.
おはようございます.不可思議な世界を生きていることを認識して生きている人はあんまいない.大人になるにつれて宇宙の成り立ちに疑問を持ったりすることも少なくなり、社会で生きていくので精一杯な人生を歩むことになるだろうと思う.こんな疑問を研究しているのは一部の賢い研究者さんぐらいモノです.
未だに無から有になったというのが分からない.それが出来れば地球上の問題はかなり解決すると思う.無から有が作れるということは物質を作れるということです.あと、色覚にも疑問を持っていてAさんとBさんが見ている色は同じ色なのかという事.色覚異常のひとは一部の色が認識できないなどがわかっているけども.そもそもAさんは赤と思っているものがBさんにとっては青だったりする事はないのかということ.これが子どもの時に抱いていた疑問です.
その疑問を生成AIに投げたらやはり同じ疑問を持っていた人がいたらしく今の答えを教えてくれました.生成AIは便利ですね.回答は下記です.
とても興味深い疑問ですね!「Aさんが見ている赤」と「Bさんが見ている赤」は、本当に同じ赤なのか? それとも、まったく違う色を見ているけれど、共通の言葉(「赤」)を使っているだけなのか? これは**「クオリア(Qualia)」**と呼ばれる哲学的な問題です。
1. 色は脳の中の解釈
色は物理的な波長として存在しますが、それを「何色」と感じるかは脳が処理する過程で決まります。目の網膜には錐体細胞(赤・緑・青の3種類)があり、これが光を受け取って信号を脳に送ります。脳はその信号を処理し、色として認識します。
2. 色の主観性(色のクオリア)
問題は、Aさんの脳が処理する「赤」と、Bさんの脳が処理する「赤」が本当に同じなのかということです。仮に、Aさんの「赤」とBさんの「青」が入れ替わっていたとしても、言葉や色の関係性(例えば信号の赤=止まれ)は学習によって決まっているので、日常生活では区別できません。つまり、お互いに「赤」と言っているけれど、実はまったく違う色を見ている可能性が理論上はありえます。
3. 色覚異常との違い
色覚異常は、特定の色の区別がつきにくくなる現象ですが、ここでの疑問とは少し異なります。色覚異常の人は「違いがわかりにくい」のであって、「全く異なる色として見ている」わけではありません。
4. 実験で確かめられる?
理論的には、「Aさんの赤」と「Bさんの赤」が違うことを確かめる方法はないとされています。なぜなら、AさんもBさんも「これは赤です」と言える以上、その主観的な体験を比べる手段がないからです。ただし、もし脳の色処理を完全にシミュレーションできる技術が生まれれば、未来では何らかの証明が可能になるかもしれません。
5. マントラッカー実験
ある種の生物(例えば特定のエビ)は、人間よりもはるかに多くの色を認識できると言われています。もし彼らに色を聞くことができたら、「人間が見ている赤」は、彼らにはもっと複雑な色として見えている可能性があります。
明日へ続く